| 神奈川県環境農政部 病害虫防除所 山口 元治 |
農産物に残留する農薬等は、人の健康に影響を及ぼすことがないよう食品衛生法により残留基準が設定され、基準を超えた場合にその農産物の流通が禁止されます。
ポジティブリストとは、その残留基準値のリスト(一覧表)のことです。平成15年の食品衛生法の改正で、ポジティブリスト制度を導入することが決まり、平成18年5月29日からポジティブリスト制度が施行されました。
5月29日まで残留農薬基準値のリストがなかったわけではありません。従来からリストはあって、その基準値を超えると農産物の流通が禁止となっていました。
では、何が変わり、どんなことが問題となるのでしょうか。
5月28日までは、ネガティブリストで規制を行っていました。ネガティブは否定で、「これはダメ」というものをリストにしていました。リストに載っている農薬の基準値を超えると流通禁止になるということです。リストに掲載されていない農薬は、残留していても規制の対象外になります。現在、多くの農産物が輸入されていますが、国外で使用される農薬には残留基準値が設定されていないものが多数あります。ネガティブリストでは、それらの基準値が設定されていないものは、規制対象外となってしまいます。
これに対し、これは流通させてよいというものをリストにしたものが、ポジティブリストです。ネガティブリストとは逆にリストにないものは全て規制され、未規制の部分がなくなります。現在施行されているポジティブリストでは、001ppmというベースとなる一律基準が定められ、リストにない農薬等は、原則001ppmが基準値として適用されます。(下表)このような制度となって、何が問題となってくるのでしょうか。 |
表1 残留基準のイメージ
○施行前の規制:赤色欄が規制対象 単位:ppm
残
留
基
準
値 |
食品名 |
農薬A |
農薬B |
農薬C |
| 米 |
0.5(残留農薬基準) |
0.5(残留農薬基準) |
基準なし |
| キャベツ |
1(残留農薬基準) |
0.2(残留農薬基準) |
基準なし |
| きゅうり |
0.5(残留農薬基準) |
基準なし |
基準なし |
| りんご |
1(残留農薬基準) |
基準なし |
基準なし |
|
 |
○施行後の規制:赤色欄が規制対象
・暫定基準と一律基準が適用され未規制部分がなくなる 単位:ppm
残
留
基
準
値 |
食品名 |
農薬A |
農薬B |
農薬C |
| 米 |
0.5(残留農薬基準) |
0.5(残留農薬基準) |
基準なし(0.01) |
| キャベツ |
1(残留農薬基準) |
0.2(残留農薬基準) |
基準なし(0.01) |
| きゅうり |
0.5(残留農薬基準) |
0.5(暫定基準) |
0.2(暫定農薬基準) |
| りんご |
1(残留農薬基準) |
0.2(暫定農薬基準) |
基準なし(0.01) |
|
| 使用基準どおり農薬を使用していれば、基準値を超えることはありません。ところが、心配されているのは、「散布しよう思っていないのにかかってしまった。」という状況で、基準値を超えてしまう可能性があるということです。特に「ドリフト(飛散)」による基準値オーバーが心配されています。 |
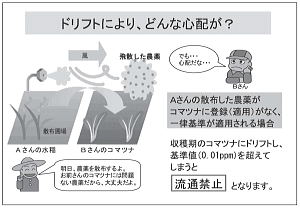 |
ドリフトを受けた作物に残留農薬基準や暫定基準が設定されていない場合に、一律基準が適用されます。計算上は、成分50%の農薬を1000倍に希釈した散布液が1㎏の農産物に目薬1滴程度(002)付着すると001ppmになります。このため、ほんの少し農薬がかかってしまっても、一律基準が適用される場合等では、基準値オーバーとなり、流通禁止となるおそれがあります。(左図)
実際に基準値オーバーとなると、出荷停止、出荷された農産物の回収、出荷前の農産物も併せて廃棄等の損害が発生する場合があります。 |
|
さらに、産地の信用失墜といった問題に発展する可能性もあり、これまで以上に周辺作物に配慮したドリフト対策が必要になっています。
農薬のドリフトは、位置、散布時の風速、散布器具の種類、散布の方向、農薬の剤型、散布量によって大きく変わってきます。(下表) |
表2 飛散に関与する要因
| 位 置 |
散布場所に近づくほどドリフトを受けやすくなる |
| 風 速 |
風速が強いほど多量に遠くまで到達する |
| 散布器具 |
手動手散布<動噴<スピードスプレーヤー |
| 散布方向 |
下に向けた散布<上に向けた散布(果樹・樹木) |
| 農薬の剤型 |
粒剤<微粒剤<液剤<粉剤 |
| 散 布 量 |
散布量が多いほどドリフト量は多くなりやすい |
|
鑑賞樹などの防除では、圧力を高め、高い所へ上向に散布することがあると思いますが、キャベツやホウレンソウ等に対する防除のように、下に向かって散布する場合に比べると、ドリフト量は多くなり、また遠くまで飛散しますので、特に注意が必要といえます。
また、残留濃度(ppm)は「農薬量(㎎)090÷作物の食べる部分の重量(㎏)」ですので、コマツナ、ホウレンソウのような軽量な作物は、キャベツ、ハクサイなどの重量がある作物に比較して、同じ量の農薬が付着しても分析すると、濃度が高くなります。さらに、農薬は時間の経過とともに減衰するので、収穫直前にドリフトを受けると高濃度になります。
このように、ドリフトによる基準値オーバーのリスクは状況によって大きく異なります。
基準値オーバーを未然に防止するために、ドリフト対策を実施する必要がありますが、対策の実施にあたっては、現場の状況を把握することが大切です。近接作物は何か、収穫期はいつなのか、使用予定の農薬の基準値がどうなっているのか等を把握し、状況に応じた対応を実施する必要があります。防除を委託された等、現場に不慣れな場合は、特に事前の状況把握は重要です。
ドリフトを減らす対策には、①風のない時を選んで散布②散布の位置と方向に注意③散布機の圧力を適切にする④散布量を適切にする⑤飛散の少ないノズルの使用⑥遮蔽シートや飛散防止ネットの設置等があげられます。
さらに、直接のドリフト防止対策に加えて、近接作物の残留基準値が大きい農薬を選択することもリスク低減には有効です。
使用する農薬の残留基準の設定状況は日本食品化学研究振興財団のホームページ等で調べることができます。
また、神奈川県病害虫防除所、神奈川県農業技術センター、各JAでも神奈川県病害虫雑草防除指針に掲載されている農薬の残留基準の設定状況に関する資料を用意し、相談を受ける体制を整えております。
農薬を散布する際は、適切なドリフト対策を組み合わせて、基準値オーバーのリスクをできるだけ減らすよう心がけていただきたいと思います。 |